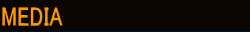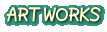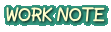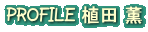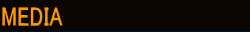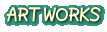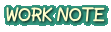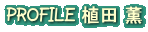|
文:谷田部淳子
 ボストンに 3カ月滞在するチャンスをもらい、モザイク発見の旅にしようと決めた。渡米の理由は、「ボストンには友達がいる」、ただそれだけだった。 ボストンに 3カ月滞在するチャンスをもらい、モザイク発見の旅にしようと決めた。渡米の理由は、「ボストンには友達がいる」、ただそれだけだった。
ボストンではホームステイをしながらモザイクを習おうと思い、massachusetts
college of art(通称マスアート)という全米唯一の州立美術学校のワークショップを受講することにした。毎週土曜の6回コースで255ドル。授業はタイルを使用しB4サイズ程度のベニヤに作品をつくるというもの。講師はブルガリア出身の画家で、「アメリカでは道具を買うことができない。アメリカにはモザイクはない」との声に、がっかりしていた。ところが、町を見渡してみると、20世紀初期のモザイクが町の中にあふれていた。ボストンやNYは周知の通り、アメリカでは古い町で、ヨーロッパ人の移住が始まった頃の、イタリア人によるズマルトの壁面モザイクや、大理石の床・天井モザイクを教会や図書館、銀行で見ることができる。ボストン市内では特にBoston
libraryの天井モザイクとMasonic Templeの5面の外壁、建物内部全体にほどこされた、床や天井のモザイクがおもしろい。またタイルモザイクを外壁につかったレストランも見ることができる。
さて、アメリカでの「モザイク」の認知度についてだが、これは高い。但し、広義のモザイクのことで、本当に色々と紹介された。最近有名なのは日本のCMでも起用されたPHOTO
MOSAIC。そして、セラミックや卵、コインにゴミ。西海岸にはstreet manがゴミやがらくたを拾って彼の生涯をかけて作った「beautifil
junk」というガウディ調の建築物もある。これは本にもなっている有名な話だ。
マスアートでのワークショップを終え、さて、何をしようかと思い、アメリカのモザイク作家に会うことにした。主だった都市のアートギャラリーは「ギャラリーブック」を発行しており、それに記載されたギャラリー・美術学校やカルチャースクールに、作家を紹介してもらえるようEメールを出しまくった。ホームページ(以下HP)・市販の本・美術誌からの情報も活用した。アメリカでは積極的な作家に多く会った。彼等はメール・HP・ギャラリーへの登録・イベント活動・ポートフォリオの作成とこまめな宣伝ツールと行動力を持つ。数名の作家にインタビューをとっての全体の印象は、モザイクはまだアカデミックな部分では認めてもらいずらいようだ、ということ。また、手間や人手がかかること、材料や道具が手に入りずらいことから、大理石やズマルトを使った大規模のモザイクを作るまで至らないという作家も意外と多かった。セラミックが主流のカルチャースクールでのクラスはいくつかあり、大学等では、西海岸はUCLAが、東海岸でもmassachusetts
college of art, Urban galassがワークショップを持ち、来期からNYUでも講座がスタートするとのことだ。
出会った作家の話をしよう。
最初に会ったのは、Sven J Warner氏。全米唯一のズマルト輸入会社の社長である。(バモント州・MOUNTAINTOP MOSAICS社)聖職者だったという彼は布を使ったモザイクと自身で開発したはさみで切れる素材(Snip tile)を利用したモザイクを楽しんでいる。それは各地のホームスクールやワシントン州での学校教材として活用されている。彼の話によると、アメリカのモザイクは、イタリアからの移民が、ズマルト・石を使い建物を装飾した1900年頃始まったようだ。世界恐慌、世界大戦時には廃れるのだが、後、富の象徴として復興する。その頃、一般市民もモザイクを楽しみたいと、テーブルや椅子の装飾へとその姿を変えていく。この時期、海のある地方(カリフォルニアやフロリダ)では、タイルによるモザイクが発達する。今でも海のある地域でのタイルやガラスによるモザイクはとても盛んだ。
そこで今度は西海岸へ。(次回へ続く) |
|
  |